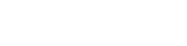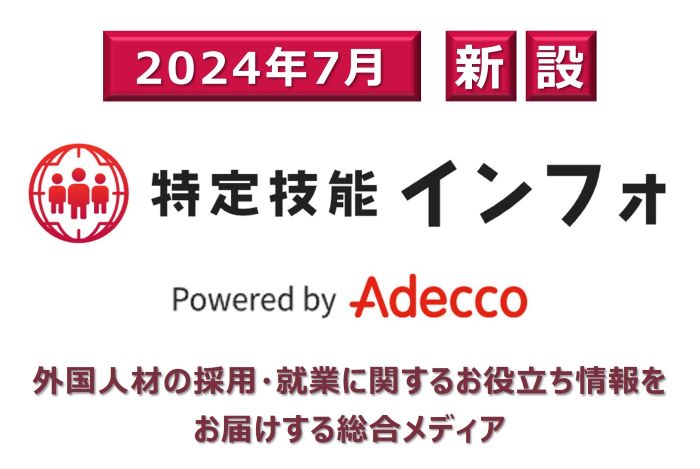本連載では、企業経営者や人事担当者の皆様に向けて、法令・コンプライアンスおよび人材関連の最新トピックスやトレンドについてお届けします。
第一回目となる今回は、弁護士であり東京都立大学法科大学院の非常勤講師を務める岩出誠氏が、現在の人事課題やトレンド、そして今後の労働法に関する予測について解説します。
今後の連載では、人的資本経営の観点も踏まえ、企業がどのように労働市場の変化や働き方の多様化に対応すべきかについて深掘りしていきます。
人事に関するお役立ち情報をお送りいたします。
メールマガジン登録
Ⅰ 現在の企業の人事課題
現在の企業の人事課題として、
- 1.企業を取り巻く環境や労働市場の変化のなか、雇用管理・ 労務管理の転換をせまられている
- 2.一方で、働く人の働く意識や働き方への希望はこれまで以上に個別・多様化の傾向を強めている
ということが挙げられます。
参考・出典:厚生労働省「新しい時代の働き方に関する研究会」報告書
1. 企業を取り巻く環境の変化
経済のグローバル化、デジタル化の進展により国際競争が激化するとともに、国際政治環境の不安定化やポストコロナ社会の到来などにより世界的に物価基調の変化が生じ、金融市場・商品市場が不安定化しています。
また、デジタル技術の革新は、事業活動に大きな恩恵をもたらすと同時に、市場や競争環境を劇的に変え、事業活動に非連続的な変化を引き起こす可能性があり、企業が直面する不確実性を生む要因の一つとなっています。
2. 労働市場の変化
人口減少、高齢化等に伴う労働市場の構造変化のなかで深刻な人手不足が起こっています。この状況は、豊富な労働力供給を前提とした従来の雇用管理・労務管理からの転換を迫っています。 また、デジタルトランスフォーメーション(DX)の進展は必要なスキルや人材に変化を引き起こし、中途採用人材の活用拡大など、 業種や職種を超えて広範に企業の人材戦略に影響を及ぼしています。
3. 働く人の意識の変化、希望の個別・多様化
職業人生の長期化・複線化が進むなかで、仕事に対する価値観や、生活スタイルが個別・多様化し、生活スタイルに応じて働く「場所」、「時間」、「就業形態」を選択できる働き方を求める人が増加しています。
また、新型コロナウイルス感染症の影響下でのリモートワークの進展を契機に、「働く場所」の選択肢が増えるとともに、オンラインでジョブマッチングが行われるプラットフォームワーカーが増加するなど、個別・多様化する働き方とキャリアに合わせて、勤務場所や勤務時間を選び、それぞれのワークスタイルに合った働き方をとることが普及しています。
こうした働き方の変化は、雇用契約の当事者である「労働者」(いわゆる「正規雇用」「非正規雇用」)にとどまらず、フリーランスなどを含む「働く人」全体に見受けられます。
4. 個人と組織の関係性
企業を取り巻く環境や労働市場の変化を踏まえ、個人と組織の関係性も変化してきています。
一方で、長期雇用の下で上司の指示に従い組織的に業務を遂行するなど、これまでと同様の働き方が馴染む労働者が今なお多く存在します。他方で、価値観や生活スタイルの個別・多様化や、環境の変化などの理由から、自発的なキャリア形成と、ライフ、キャリアの各ステージにあわせた多様な働き方を求める労働者も増えています。 そのため、企業に対して、ライフ、キャリアの各ステージの変化に応じた多様な働き方ができることや、能力を高め、発揮し、豊かなキャリアを形成できる機会の提供を求める者が増加していますので、これらへの対応が課題となります。
Ⅱ 現在の企業の人事トレンド
1. 組織について
現在の企業の人事トレンドとして、上記Ⅰのような企業を取り巻く環境や、労働市場の変化に対応するためには、企業が長期的な視点に立って優れた人材を確保し活用することが重要になっています。
今後、企業はこれまでと比べ、「柔軟な発想で新しい考えを生み出すことのできる能力」を重視する方向に向かうと考えられています。そのため企業においては、長期雇用や企業内キャリア形成を重視しつつ、労働者の能力や成果を評価した上で処遇や人材配置などに反映していく仕組みが広がっています。
こうしたことから、働く人の多様で主体的なキャリア形成を支援しつつ、 「パーパス(企業の存在意義)経営」を推進するために、エンゲージメントを高める、求める人材像や能力の見える化を図る、「1on1ミーティング」(定期的に部下と上司が1対1で行う面談)などにより労働者とのコミュニケーションを図るなどの取組みを重視する企業が増えてきています。
2. 個人と組織の関係性について
このような変化を背景として、組織と個人の関係性についても、両者が長期的に良好な関係を保っていくため、次のような変化がみられています。
- (1)企業は、働く人に対して、正規雇用・非正規雇用の雇用形態などにとらわれず、全ての働く人が希望に沿って働き方を柔軟に選択し、能力を高め発揮できる環境を提供する
- (2)働く人は、自発的に働き方とキャリアを選択した上で、企業に対して能力を発揮し成果を上げる
以上の組織と個人の関係を形成し安定的に維持するためには、集団的な労使の協議・交渉や個別面談などによる労使の個別的な意思疏通、イントラネットを活用した労使間の意見・情報の共有など、多様なチャネルを通して労使コミュニケ-ションを図っていくことが重要です。 これからは、全ての働く人が将来のキャリアを見据えて企業の枠を超えて働ける環境の整備が人事のトレンドとなっていきます。
3. 具体的実践例
以上の人事トレンドの具体的実践例として、以下の点が指摘されています(詳細は、報告書5頁以下と研究会が公表している関連資料参照)。
- (1)集団・個別双方の労使コミュニケーションを行いながらの雇用管理・労務管理の実施
- ポストごとの職務・必要能力などを明確化し、社員とのコミュニケーションをとりつつキャリア形成を支援している企業もあります。
- リモートワークを活用する中で、育児や介護の都合に応じて柔軟に働ける環境を整え、結果として育児や介護中の社員でも希望する者は時短ではなくフルタイムで働けている企業もあります。
- (2)健康管理・職場環境改善を重視し、社員とのコミュニケーションを踏まえての改善
法定の健康管理を超えた、職場環境改善のための取組みの積極的な実施など
Ⅲ 今後の労働法関連予測
以上の人事上の課題とトレンドを分析した報告書を踏まえて、厚労省では、令和6年1月23日から5月10日まで、既に7回の研究会を開催し、急ピッチで労基法による規制への全面的見直しを進めてきています。第6回で、「これまでの議論の整理」も公表されており、下記の改正検討項目の審議が進められているため、今後の立法化への動きを注視していく必要があります。
1. 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 |
|
|---|---|
| 1-1 最長労働時間規制 |
(1) 時間外・休日労働時間の上限規制 (2) 労働時間の意義等 (3) 裁量労働制・高度プロフェッショナル制度・管理監督者等 (4) テレワーク等の柔軟な働き方 (5) 法定労働時間週44時間の特例措置 |
| 1-2 労働時間からの解放の規制 |
(1) 法定休日制度 (2) 勤務間インターバル制度 (3) 年次有給休暇制度について (4) 休憩について |
| 1-3 割増賃金規制 |
(1) 割増賃金の趣旨・目的 (2) 副業・兼業の場合の割増賃金 |
2. 労働基準法の「事業」について |
|---|
3. 労働基準法の「労働者」について |
|---|
|
(1) 労働者性の判断基準と予見可能性 (2) 労働基準法以外の法令の対象範囲 (3) アルゴリズムによる使用者の指揮等新しい労働者概念 (4) 家事使用人 |
4. 労使コミュニケーションについて |
|
|---|---|
| 4-1 集団的労使コミュニ ケーションの意義と課題 |
(1) 集団的労使コミュニケーションの意義と課題 (2) 労使協議を行う単位 |
| 4-2 過半数代表者による労使 コミュニケーションの課題 |
(1) 過半数代表者に関する課題 (2) 過半数代表者の選出手続 (3) 過半数代表者による意見集約の仕組み (4) 労働者への支援の仕組み (5) 過半数代表者以外の仕組み (6) 個別の労使コミュニケーション |
「これまでの議論の整理」をまとめると、それぞれの項目で以下のような内容が議論され、令和6年5月10日の第7回では、労使の代表からの意見表明もなされています。
参考・出典:一般社団法人日本経済団体連合会「今後の労働基準関係法制に経済界として求めること」
参考・出典:日本労働組合総連合会「労働基準関係法制のあり方に関する連合の考え方」
1. 労働時間法制
労働時間の上限規制、勤務間インターバル、年次有給休暇の取得促進、割増賃金規制などが議論されています。特に、テレワークの普及に伴い、柔軟な働き方と労働者の健康確保を両立させるための具体的な規制強化が求められています。
2. 労働基準法の「事業」
事業場単位での規制の有効性と企業単位化の効率化が議論の中心です。特に、テレワークや分散勤務の増加に伴い、事業場の概念や適用単位を再検討し、使用者の責任範囲を明確にする必要があります。
3. 労働基準法の「労働者」
労働者性の判断基準を明確化し、フリーランスやプラットフォームワーカーも含めた保護の強化が議論されています。労働者であると推定する方式や判断基準のチェックリストの導入が検討されており、予見可能性の向上が求められています。
4. 労使コミュニケーション
労使間の対話を促進するため、集団的および個別的な労使協議の強化が議論されています。過半数代表者の選出手続の適正化や教育・研修の支援、労使委員会の設立など、労使コミュニケーションの基盤強化が重要視されています。
Profile

<著者略歴>千葉大学人文学部法経学科卒業、東京大学大学院法学政治研究科修了、厚生労働省労働政策審議会労働条件分科会公益代表委員、青山学院大学客員教授、千葉大学客員教授、明治学院大学客員教授を歴任、東京都立大学法科大学院非常勤講師、弁護士法人ロア・ユナイテッド法律事務所代表パートナー(現任)
<著作等> 「労働法実務大系」第2版〔民事法研究会〕等著作・論文多数