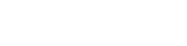本連載では、企業経営者や人事担当者の皆様に向けて、法令・コンプライアンスおよび人材関連の最新トピックスやトレンドについてお届けします。
第2回目となる今回は、弁護士の木原康雄氏が、AIの活用が雇用・労働市場にどのような影響をもたらし、人事関連の法的な課題にどのように留意する必要があるのかを解説します。
人事に関するお役立ち情報をお送りいたします。
メールマガジン登録
Ⅰ AIの活用と雇用・労働市場の流動化の促進
1. AIによる仕事のデジタル化
近年、AIの活用による業務のデジタル化が進んでいます。AIに過去の大量のデータをインプットすることで、現在の問題に適合する情報を選別し、解決策を提示することも可能です。例えば、弁護士の仕事においては、過去の裁判例を検索したり、契約書のチェックを行ったりすることができます。
2. AIに取って代わられる業務
これらの作業は現在人間が行っている仕事の一部であり、特に形式的で定型的な業務はますますAIに取って代わられることが予想されます。結果として、人間が行うべき仕事は、そのような形式的で定型的な業務の結果をもとにした、創造的かつ専門的な経験を要する判断業務へとシフトしていくでしょう。
3. 創造性・専門的経験の重要性
創造性や専門的経験は短期間で身につくものではない一方で、AIの導入速度は加速しています。企業は、創造性や専門的な経験を既に持つ人材を中途採用することに力を入れるようになるでしょう。また、労働者も、自らの創造性や専門的な経験を最大限に活かし、より良い待遇を求めて転職を考えるようになります。
このようにして、AIの進化・活用により、雇用・労働市場の流動化が促されることが予想されます。
Ⅱ 企業の秘密保持への対応における留意点
1. 秘密の流出リスク
雇用の流動性が高まり、創造性や専門的経験を持つ人材の転職が増えると、企業は営業秘密やノウハウの流出を懸念することになるでしょう。
転職者が、技術情報や仕入れ情報などを転職先である競合会社に開示し、競合会社がそれを利用して企業活動を行ったとして、不正競争防止法違反を問われる事例が増えています。また、就業規則上の秘密保持義務違反であるとして、懲戒解雇や退職金を不支給とされるケースも増えています。
2. 競業避止特約の必要性と注意点
企業は事前の対処方法として、例えば退職者との間で競業避止特約を結んでおき、予め競合会社への転職ができないようにしておきたいと考えるでしょう。
ただし、裁判例では、いかなる競業避止特約でも認められるわけではない点に注意が必要です。以下の要素を考慮してその有効性が判断されます。
- (1)守るべき企業の利益:当該退職者との関係で、企業側に守られるべき具体的な利益が存在するかどうか。
- (2)退職者の地位:退職者が企業内でどのような地位にあったか。重要な情報にアクセスできる立場にあったかどうか。
- (3)地域的な限定:競業避止義務の地域的範囲が過度に広くないか。
- (4)競業避止義務の存続期間:競業避止義務の期間が長すぎないか。
- (5)禁止される行為の範囲:禁止される行為の範囲が広範すぎないか、具体的に明示されているか。
- (6)代償措置:競業避止義務に対する代償措置が講じられているか。
競業避止特約による転職の制限が、必要性と合理性の有無・程度に照らし過度なものであると判断される場合には、公序良俗に反し無効であると判断されます。
そのため、企業はこれらの点を慎重に検討し、競業避止特約が法律的に有効であることを確認する必要があります。と同時に、特約の具体的な内容や条件が明確であり、合理的なものであることを従業員に説明し、納得してもらうことが重要です。また、競業避止特約の内容については、定期的に見直しを行い、現状に適合しているかを確認することも必要です。
これにより、企業は貴重な営業秘密やノウハウの流出を防ぎつつ、法律的に有効な手段を講じることができます。
Ⅲ 人員整理における留意点
1. 高い創造性・専門性を持つ人材の中途採用
経営や市場の状況変化により、その職務の必要性がなくなる場合があり得ます(例えば、売上減少による当該業務・部署の廃止による場合など)。
そのような場合、企業は人員整理を検討するかもしれません。しかし、裁判例上、整理解雇が有効とされるためには、以下の要素が求められます。
- (1)人員削減の必要性
- (2)解雇回避努力
- (3)被解雇者選定の妥当性
- (4)手続の相当性
これらの要素を総合的に考慮した上で、客観的合理的理由・社会的相当性が認められる必要があるものとされています。
したがって、単に業務・部署がなくなったということだけでは、整理解雇は有効とは認められないことに注意が必要です。
2. 具体的な裁判例
最一小判令5.8.3では、ある特色をもった労働者の整理解雇の有効性が議論されました。すなわち、この労働者は、高度専門職であり特定の職種に従事し、高待遇を受けていました。そのため、転職によってキャリアアップを図り、さらに高い待遇を得るというキャリア形成に適合しており、終身雇用や年功型賃金制度の適用を受ける従来型の労働者とは異なるという特色があったのです。
もっとも、裁判では解雇の有効性を慎重に判断する必要があるとし、上記特色によって判断要素自体を変更することはせず、従前どおりの上記4つの要素に基づいて検討するとされました。
その結果、労働者が所属していた部署が廃止されたことだけでなく、会社が労働者の意向や希望を聴取し、適切な社内公募のポジションを提示したことが評価されました。さらに、募集要件を満たさないポジションについても可能な限りサポートを申し出るなど、労働者がグループ会社内で働き続けられるようにするための手段を提供した点も考慮されました。加えて、退職金以外に一定の金銭を支払う退職パッケージを提示したことも、解雇回避努力の一環として評価されました。
これらの取り組みを総合的に判断し、会社側の解雇回避努力や手続の相当性を認め、整理解雇が有効とされました。
参考・出典:労働経済判例速報2525号24頁 最一小判令5.8.3
Ⅳ 人材の適性を正しく見極めるための留意点
1. 高度な専門性を持つ人材の採用
労働市場の流動化により、企業は高度な専門性や能力を持つ即戦力の中途採用に注力するようになります。採用プロセスでは、応募者の専門性や能力を評価するためにAIを利用するケースも増えるでしょう。
2. AIの限界と注意点
AIは応募者の職務経歴書や面接内容をもとに評価しますが、これらのデータは応募者自身が提供したものであるため、真実性の判断は難しい場合があります。例えば、応募者の経歴や能力を見込んで採用したものの、実際にはその期待に応えられなかったケースも考えられます。また、勤務態度やコミュニケーション能力、協調性など、言語化しにくい要素はAIでは判断できません。
3. 試用期間内での対応
試用期間内で能力不足が判明した場合、本採用を拒否することができます。しかし、これには客観的で社会的に見て適切な理由(客観的合理的理由・社会的相当性)が必要です。これが認められるには、履歴書等では見極められなかった不適性等が判明したものであることと、指導やサポートを行ったものの改善しなかったという事実関係が重要です。
4. 普通解雇の要件
試用期間を過ぎた後での解雇を検討する場合、以下の要件を満たす必要があります。
- 客観的合理的理由:能力不足が明確であり、改善の見込みがないこと。
- 社会的相当性:社会的に見て解雇が適切であること。
裁判例では、企業が適切な指導やサポートを行ったにもかかわらず、労働者が改善しなかった場合に普通解雇が有効と認められています。
5. 具体的な裁判例
例1:米国の法科大学院を卒業し、ニューヨーク州の弁護士資格を持つ労働者が、外資系日本支社のリーガルカウンセルとして高賃金で雇用されましたが、期待されるパフォーマンスを発揮できず、他の社員との協力も不十分でした。企業は具体的な要望を伝え、パフォーマンス改善プログラムを実施しましたが、労働者は改善せず、普通解雇が有効とされました。
参考・出典:労働経済判例速報2440号17頁 東京地判令2.6.10
例2:他の従業員との協調性やコミュニケーション能力が不足していた労働者が、本採用を拒否されました。上長は協調性やコミュニケーションについて指導を行いましたが、労働者は改善せず、他の従業員を批判するなどの行動を続けました。この場合も本採用拒否が有効とされました。
参考・出典:労働判例ジャーナル140号46頁 東京地判令5.2.22
AIを活用して高度な専門性を持つ人材を採用する際には、AIの限界を理解し、試用期間中に適切な指導やサポートを行うことが重要です。能力不足が判明した場合は、客観的合理的理由と社会的相当性を備えた対応を行う必要があります。
Ⅴ まとめ
以上のとおり、AIの活用は、雇用・労働市場の流動化を促進させますが、企業にとっては労働者の競合企業への転職や、能力不足による解雇の問題など、法的な留意点が多く存在します。これらのポイントを理解し、適切に対応することが求められます。
Profile
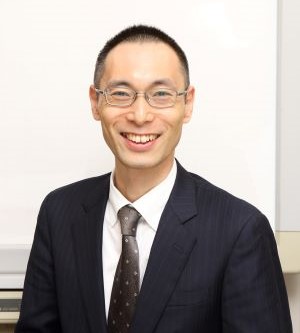
<著者略歴> 1998年早稲田大学法学部卒業。2003年弁護士登録(東京弁護士会)。「ハラスメント対応の実務必携Q&A」(2023年、民事法研究会、共著)等を執筆。